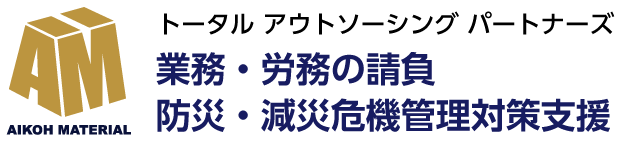避難生活の心得
2016年4月の熊本地震や2018年7月の西日本豪雨災害、もちろん東日本大震災や能登半島大規模災害の時も、ライフラインがストップし、避難勧告が発令され避難を余儀なくされた方々は様々な非日常的で困難な生活を強いられました。
普段から災害備蓄品を十分に備蓄されていたご家庭は全体の5%程度で、備蓄品の購入金額もほとんどのご家庭で1万円以下でした。
平素の生活では『有って当たり前』の生活必需品が避難生活では不足します。
電気・水道・ガスが止まった場合に最も必要とされる物は、飲料・食品・トイレ・明かり・乾電池・モバイルバッテリー・ラジオ・衛生用品等です。
また、避難生活が長くなるとお風呂に入れなかったり、トイレが不衛生だったり、避難所の床が硬くて寝くれない、プライバシーが守れない等、劣悪な状況が発生します。
自治体は被害を少なくするために避難勧告や避難命令を出しますが、予想していたよりも避難所への避難は50%程度で、その理由としては『高齢者や乳幼児がいる。』『避難所の場所が分らない。』『避難所が遠い。』『感染症が怖い。』等で、在宅避難や親戚知人宅であったり、車中で過ごす方が多く見られました。
台風や豪雨の被災者は在宅避難をする割合が多く、新型コロナやインフルエンザなどの感染症の影響による3密(密集、密接、密閉)を避けるため、今後は特に車中泊避難が増えていくことが予想されますが、感染症のリスクは有っても人命を優先させるためには避難所や安全な場所への避難が大切です。
指定避難場所や在宅避難でも、自助・共助・公助を念頭に、日頃から災害備蓄を心掛けて、先ずは自らの命を守り、相互に協力し助け合い、地域全体の安全と安心を図ることが何よりも重要で、従来の生活に戻る最良の選択肢です。