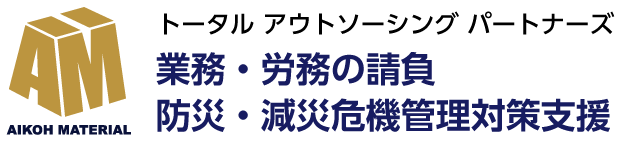災害備蓄品の管理
《場所》
- 備蓄品の管理・維持は計画的になされているか。
・多種多様な備蓄品を使用目的別に分け、総合的に管理する。
- 備蓄品の設置場所、設置施設は適切か。
・水や食料、防災倉庫や備蓄棚等の一定の場所で保管し、適量であることを把握する。
- 設置場所施設のカギの管理、保安年の不備は無いか。
・マスターキーの管理は災害備蓄品管理責任者が主に担当する。
- 耐震・耐火の安全面での配慮はなされているか。
・同一事業所内であれば一応の安全は確保されている。
・土地や立地の条件により1階ではなく2階以上へ敢えて分散備蓄させる。
- 設置場所の通気・換気は十分か。
・保存水や食料品の保管上、通気口・換気口は重要。
- 備蓄箇所が分りやすいように案内表示はされているか。
災害備蓄品管理責任者が不在の場合、誰でも場所が特定でき解錠できるようにする。
- 設置場所の環境は保たれているか。
・湿度や温度は適切に管理する。
《運用・管理》
1,災害発生時に備蓄品が滞りなく使用できるか。
・あらかじめ作成された計画表に基づき配布する。
2,備蓄品の数量や品目の確認と仕分け
・各部署や各家庭に割り当てられた数量を速やかに配布し、不足分を補充する。
3,備蓄品の保存期限、賞味期限、対応年数を管理。
・備蓄品管理表を作成し、体系的に管理する。
・この作業が危機管理上最も重要な作業であり、会社や家庭の存続が問われる項目。
4,備蓄品の使用目的・内容が把握され、表示されているか。
・誰でも一目でわかるように表示する。
5,備蓄品の管理記録を保存する。
・備蓄品種類によっては納入日が同じでも保存期限・賞味期限が異なるものがある。
・各期限前に入れ替え、廃棄ロスが無いように配布・消費する。
6,被災時の対人リレーションは構築されているか
・BCP、LCP対策の一環で伝達・命令系統をわかりやすくし、上意下達を徹底する。
7,前任者との引継ぎを確実にする
・書類だけでなく、備蓄品の状態や内容も引き継ぎ、マニュアルの修正や追加も実施。
《大型資機材》(企業、施設、団体の場合)
1,防災倉庫などの施設に集中備蓄しているか。
・備蓄スペースの平面図を作成し、何がどこにあるのか把握しわかりやすくする。
2,燃料等の火気注意は徹底されているか。
・火気管理者を決め、火気厳禁を表示する。
3,消火器や火災報知機の対応年数や使用期限は確認されているか。
・消防法確認と法令に従った交換を確実に実施する。
4,定期的に稼働確認しているか。
・定期的に動作確認を実施し、蓄電装置は負荷をかけて稼働状況の確認も実施する。
5,大型資機材の運搬方法は考慮されているか。
・運搬手段として事前にリヤカーや台車、コンテナ車などは保有しているか確認する。
『備蓄品は、誰でもすぐに使える場所に保管しよう』
勤務先から離れた場所に保管している場合、災害発生時に保管場所まで取りに行かれない事態も想定されます。
特定の場所だけに備蓄品を集中させるのではなく、各フロアの休憩室や会議室の空きスぺースに分散備蓄することも有効です。
《企業の災害備蓄対策》
企業が災害備蓄対策を考える上で最も重要なことは「事業継承計画(BCP)」であり、災害備蓄対策の中の一つの大きな柱であると言えます。
BCP対策には、①人命の救助 ②商品・製品・サービスの供給 ③地域との共存や二次災害の防止がありますが、人命の安全を図る上では最優先の課題として社内備蓄を徹底させ、リーダーシップのとれる災害備蓄品管理者を各部署に配置し、社内の連携を図ることで不測の事態に対応することが重要です。
災害備蓄品の中には、水や食料をはじめとする飲食料品、簡易トイレ、毛布や明かり等の生活必需品、発電機、蓄電池、浄水器、工具類などの防災資機材、そして安否確認や各種情報通信サービスなど、多種多様なものが有ります。
BCPの策定が叫ばれる今日、「防災」と「事業継承」の関係を論ずるより、今まで実施してきた防災対策に事業継承の観点をプラスしていくことが企業防災の推進であると言えます。
企業は、社員や職員の安全を守るために最低限の防災・災害の知識と情報として社内災害備蓄の管理の実践をお薦めいたします。