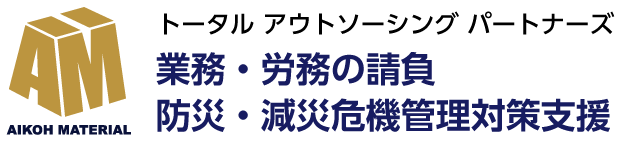最近、インターネット上で「2025年4月26日に首都直下地震が発生する」という予言が話題になっています。
また、首都直下地震は「今後30年以内に70%の確率で発生する」という政府の公式見解も広く知られています。
これらの情報の真偽や根拠について、科学的な視点から詳しく解説します。
特に科学的な予測と霊能者の予言の違い、そして実際にどのような備えが必要なのかを明らかにしていきます。
「2025年4月26日」の首都直下地震予言。
これは沖縄の霊能者によるのだとされています。
その予言によると、2025年4月26日に関東地方を震源とする震度6以上の巨大地震が発生し、さらに地震発生から93分後に東京湾を最大30mの津波が襲うというものです。
特に「湾効果」により津波の威力が増幅される可能性があるとされています。
また別の予言者の方も、2025年7月5日に大津波が発生すると予言しており、これが南海トラフ地震に関連しているとの見方もあります。
しかし重要なのは、これらはあくまで「予言」であり、科学的な根拠に基づいた予測ではないという点です。
沖縄の霊能力者については「過去の的中率が高い」という噂もありますが、科学的検証を経たものではありません。
首都直下地震とは何か?
その噂の信憑性を検討する前に、そもそも「首都直下地震」とは何かを理解しておく必要があります。
平成26年版防災白書によれば、首都直下地震とは「首都及びその周辺地域の直下で発生するマグニチュード7クラスの地震及び相模トラフ(相模湾から房総半島南東沖までの海底の溝)沿い等で発生するマグニチュード8クラスの海溝型地震」と定義されています。
つまり、首都直下地震は東京を含めた近隣地域で発生する規模の大きな地震を指し、予想される最大震度は「震度7」です。
最悪の場合、死者2万3000人、経済被害は95兆円に達すると想定されており、日本の首都機能に甚大な影響を与える可能性があります。
「今後30年以内に70%」の科学的根拠では、政府が公表している「首都直下地震が今後30年以内に70%の確率で発生する」という予測は、どのような科学的根拠に基づいているのでしょうか。
8つの大地震をベースにした計算2014年、政府の地震調査委員会が示した「今後30年で70%」という数字は、過去に発生した8つの大地震を根拠にしています。
具体的には以下の地震です:
1782年 8月23日「天明小田原地震」(M7.0)
1853年 3月11日「嘉永小田原地震」(M6.7
1855年 11月11日「安政江戸地震」(M6.9)
1894年 6月20日「明治東京地震」(M7.0)
1894年 10月7日「東京湾付近の地震」(M6.7)
1895年 1月18日「茨城県南部の地震」(M7.2)
1921年 12月8日「茨城県南部の地震」(M7.0)
1922年 4月26日「浦賀水道付近の地震」(M6.8)
これらの地震は、1703年の「元禄関東地震」(M8.2)と1923年の「大正関東大震災」(M7.9)の間の220年間に発生したものです。
地震調査委員会は、これらのデータを元に「ポアソン分布」という確率計算法を用いて将来の地震発生確率を算出しています。
ポアソン分布とは、発生確率が低い現象が長期間においてどのような頻度で発生するかを表す確率分布です。
1838年に数学者シメオン・ドニ・ポアソンによって発表されました。
具体的な計算方法は以下の通りです:
220年間で8回の地震が発生したため、平均発生間隔は220÷8=27.5年と計算されます。
この平均発生間隔をポアソン分布の式に当てはめます。
P(x) = (λ^x / x!) * exp(-λ)
ここで、λは単位時間あたりの平均発生回数、xは発生回数、exp(-λ)はeの-λ乗です。
30年間での平均発生回数λは、30÷27.5=1.0909回となります。
30年間で地震が発生しない確率を求めるため、x=0をポアソン分布の式に代入します:
P(0) = (1.0909^0 / 0!) * exp(-1.0909) = 0.3359
よって、30年間で地震が発生する確率は、1-0.3359=0.6641、約70%と計算されます。
このように、首都直下地震の「30年以内に70%」という数字は、過去の地震発生パターンを統計的に分析した結果であり、数学的根拠に基づいた予測なのです。
首都直下地震に最も類似する「安政江戸地震」8つの大地震のうち、特に現代の首都直下地震に類似すると考えられているのが、1855年に発生した「安政江戸地震」です。
この地震は、ペリー提督が黒船で来航した2年後、第13代将軍・徳川家定の時代に発生しました。
震源は東京湾北西部とされ、当時の江戸の広い範囲が激しい揺れに襲われました。
特に被害が大きかったのは、現在の千代田区丸の内(当時の江戸城の東側)、墨田区、江東区、そして横浜市周辺でした。
約1万5,000軒の家屋が倒壊し、火災も発生。
死者は7,000人以上に上ったとされています。
現在、超高層ビルが建ち並ぶ東京の中心部が、同様の地震に襲われた場合のことを想像すると、その被害規模の大きさが懸念されます。
切迫する首都直下地震過去の地震活動を詳しく分析すると、さらに興味深いパターンが浮かび上がります。
専門家の中には、220年間の地震活動には「静穏期」と「活動期」があると指摘する人もいます。
期間前半の100年間はわずか1回しか大地震が発生していないのに対し、期間後半ではより頻繁に地震が発生しています。
特に「関東大震災」の前年とその前年に合わせて2回、1894年から翌年にかけては3回と、大地震が相次いでいました。
「関東大震災」(1923年)から今年(2025年)で約102年が経過しており、これから活動期に入る可能性が指摘されています。
歴史をさらにさかのぼると見える「周期性」さらに歴史をさかのぼると、約1100年前の9世紀に以下の3つの大地震が発生していたことがわかっています:
869年「貞観(じょうがん)地震」
878年「元慶(がんぎょう)関東地震」
887年「仁和(にんな)地震」
「貞観地震」は東北の太平洋沖合で起きたマグニチュード8を超える巨大地震で、2011年の東日本大震災に類似していると言われています。
注目すべきは、貞観地震の9年後に「元慶関東地震」が発生したことです。
もし2011年の東日本大震災が「貞観地震」に相当するとすれば、9年後の2020年ごろに「元慶関東地震」に相当する地震が発生する可能性があったことになります。
現在は2025年ですので、その時期をすでに過ぎていることになります。
これらは限られた歴史記録に基づく推測にすぎませんが、地震活動には一定の周期性がある可能性を示しています。
科学的予測と「予言」の違いここで重要なのは、科学的な予測と霊能者などによる「予言」を区別することです。
科学的予測:
過去の観測データに基づいている統計的手法や物理モデルを用いている確率で表現され、絶対的な断言ではない検証可能な方法論を採用している
予言:
個人の感覚や霊感に基づいている科学的な検証が困難
具体的な日時を断言することが多い
検証方法が明確でない
2025年4月26日の予言については、科学的根拠に基づくものではなく、個人の霊感や予知能力によるものと
されています。
一方、「30年以内に70%」という予測は、過去の地震発生データを統計的に分析した結果です。
「信じるか信じないかはあなた次第」と言えますが、防災対策を考える上では、科学的な予測を基本としつつ、「いつ起きてもおかしくない」という前提で備えることが重要です。
【一部ネット掲載の関連記事から引用】
#防災
#防災危機管理
#首都直下